現在の神奈川県鎌倉市山崎の中央公園内に魯山人の桃源郷があった‥‥
大正15年、魯山人の次男武夫が心臓病を患い16才で亡くなった年の秋から暮れにかけて鎌倉山崎に広大な土地を借りた。陶房として必要な工房などを建て、山の頂に京都風の登窯(ほしがおかがま・星岡窯)を築窯することにした。
その頃の山崎は、あたり一帯、長閑な田園地帯が拡がり、鎌倉特有の谷戸のいたるところから清水が染みでるような土地柄で棚田もあった。

前方の峠を越えれば梶原方面へ)
京橋の「大雅堂」美食倶楽部会員であった長尾半平(東京市電気局長)の斡旋によって、赤坂山王台日枝神社境内にあった旧華族会館「星岡茶寮」を借り受けた魯山人は、ここで高級料亭を始める準備にとりかかる。京橋の美食俱楽部を経て立ち上げた「花の茶屋」では菁華窯で制作した器に料理を盛り付けて評判となり、自信を得た魯山人はスケールの大きな料亭「星岡茶寮」で使用する食器を制作するための場所を探しはじめた。
誰よりも自然とともに生きる精神的な芸術形成の場所に憧れていた魯山人は、円覚寺の前にあった自宅から神社仏閣をくまなく散策した。山ノ内、台、離山などにあった円覚寺はもとより明月院、建長寺、光照寺、常楽寺、多聞院方面へ、さらには山崎へも足を延ばした。それぞれの寺社が谷戸に存在するように思えた。
ここは鎌倉時代、鎌倉と各地を結ぶ主要な鎌倉街道。『従是江のし満』という山崎道標が立っており、鎌倉時代には「戦いの神」として信仰され、江戸時代には庶民の間で流行していた江の島参りに通じるところだった。江の島信仰人たちはここ山崎から山を登って富士塚を通り、江の島へ下って行ったのだろうか。
山崎バス停から公園に向かう途中-1.jpg)
鎌倉街道中ノ道を小袋谷から東へ歩くと二股に分かれていた。その角に庚申塚があり、『見猿・聞か猿・言わ猿』が可愛らしく並んで刻まれている。魯山人は神明神社の急な階段を上り、神社の脇にある獣道のような細い道を登り詰めるとそこは鬱蒼とした松林であった。ここから松林を透かして倉久保の谷戸が観えた。
ここは南北に高さ5.60mほどの山々に囲まれ、「隔離された自然を抱く別世界。自らの桃源郷を創り、登窯を築くには絶好の場所だ」思い、ここ山崎に約7千坪の土地を山崎四十数軒の共同所有者から借りた。山林4273坪、畑1475坪、田943坪である。ようやく魯山人窯藝研究所:星岡窯(ほしがおかがま)築窯の準備をはじめたのだ。
昭和3年晩秋、星岡窯全景‥‥神明神社からの松林を透かして見えた倉久保の谷戸であった。

まず、最初の東屋として裏山の中腹に八角建の咏歸亭(詠歸亭・建坪4坪)を大正15年秋に建てた。柳生笠のような茅吹き屋根が印象的だった。

つづけて観楓亭、頂上付近に富士山が観える富士見亭を建て、昭和2年2月、京風登窯を築窯した。星岡茶寮の登窯ということで「星岡窯」(正式名:ほしがおかがま)と名付けた。
「芸術家には夢がなければいけない…いいものには境がない」というのが魯山人の持論で、この山崎の別天地を気に入り、そんな意味から、『夢境』を号とした。昭和2年7月に茅葺き屋根の「夢境庵」(建坪13坪)を自身の設計で建てた。魯山人の仮寓と茶室を兼ねる瀟酒な数寄屋造りとした。(戦後には上絵付けや叩き成型、轆轤による削りの仕事をする魯山人専用の仕事場となった。)
-1024x456.jpg)
右)慶雲閣は焼失し、山門も2022年8月 朽ち果て取壊わされた
昭和2年5月には窯の雨除けとなる屋根とともに本焼に必要な窯道具置場(22坪)を建て、制作する仕事場(33坪)を建てた。三分の一を制作場として使用、他は研究員という弟子たちの住居に充てられた。
同9月には古陶磁参考館『第一参考館』(建坪36坪)を建てた。平屋の第一参考館は、当初、千七百点を陳列していたが、その後、参考品の点数も増えて3500余点におよぶ古陶磁を収蔵し「座辺師友」とした。それは「学者の参考書籍」に匹敵するもの。

(「星岡」より)
私は16歳の時、魯山人に促されて第一参考館に入ることができた。魯山人が座右銘とした『温故知新』(徳川家達、頭山満、正木直彦、根津嘉一郎らが揮亳)の扁額が部屋ごとに掲げられており、ガラスケースには多くの古陶磁が整然と並んでいた。この部屋に入った時、その制止した冷たい空気の中で凛とした緊張感を覚えたものである。当時は来訪者の参観にも供していた。
同2年10月には建坪30坪の建物を小坂小学校の裁縫室を移築して窯の向かい側に第二陳列館『第二参考館』を建てた。2階の20坪を魯山人の作品を凛冽した応接間兼ギャラリーとして登窯からは来訪者らを直接、入行けるようにした。1階は30坪、瀬戸美濃系の古陶磁などを陳列した。ここから露地を通って無境庵に通じていた。
山崎にある魯山人邸の総建坪は368坪(建物11棟、附属建物9棟、亭3棟)、合計23棟となった。
神明神社から臥竜峡と名付けた切通しを抜け、茅葺切妻の山門を潜ると、孟宗竹を透かして聳え立つ茅葺きの書院造りの建物が目に入る。これが気品さえ感じられる『慶雲館』であった。

右下に古陶磁参考館の「第一参考館」、左前方には「夢境庵」

昭和3年9月、相模国高座郡御所見村用田(現在の神奈川県藤沢市用田)の伊藤祐吉家にあった徳川初期の屋敷(33.5坪)を、久邇宮邦彦王(くにのみや くによしおう)の計らいで鎌倉山崎に移築したものだ。
明治14年4月28日と30日の両日、明治天皇が陸軍大演習のとき、近衛兵不期對抗運動を天覧して、その折、伊藤家の貴賓館で御休息され、後に伏見宮貞愛親王、閑院宮戴仁親王殿下が各一泊された所である。伊藤家は1927年(昭和2年)3月から発生した経済恐慌(金融恐慌)によって没落し、その後、久邇宮邦彦王殿下が所有していた。魯山人はその貴賓館を見て気に入り、譲り受けて山崎に移築して「慶雲館」と名づけた館で、昭和10年に「慶雲閣」と改名している。(食客時代、長浜にあった明治天皇の行在所として建てられた「慶雲館」に肖った名前。昭和17年から自宅とした。

右:慶雲閣と、その前庭に広がる蓮池
(ともに第54回魯山人展個展案内より)
東南には脚高の濡れ縁がL字型に配されている。前庭には蓮池を掘った。この池には牛蛙(体長15センチほどの食用蛙)が沢山いて、夕方にはいっせいに鳴き出し、臥龍峡あたりにも聞こえた。魯山人は後ろ脚の皮を剥き、野菜の餡かけムニエルにする。ワイン仕上げの白い身を取り分けキリンビールを片手に上機嫌だった。

魯山人の終の住いとなった「慶雲閣」。惜しむらくは平成10年(1998)8月3日の午後7時45分、野村証券の北裏喜一郎氏の別荘「其中山房」とされていた「慶雲閣」が放火され、犯人は隣接していた茶室「夢境庵」で焼身自殺して、ともに焼失してしまう。私が最後に慶雲閣を見た1週間後のことであった。残ったのは山門と歿後、河村喜太郎が引き取った登窯だけとなってしまった。
魯卿あん【大藝術家 北大路魯山人展】
2025年4月14日(月) ~ 4月26日(土)
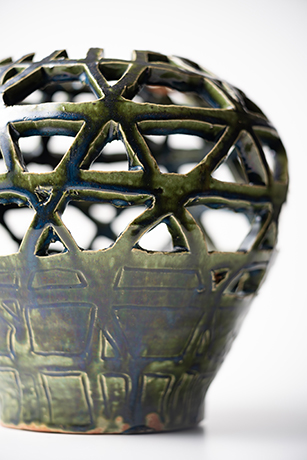
☆★☆
魯山人「大雅堂」「美食倶楽部」発祥の地
〒104-0031 東京都中央区京橋2-9-9
TEL: 03-6228-7704
営業時間:11:00~18:00(日・祭日休)
無二の個性豊かな陶芸家とともに歩む
〒150-0002 渋谷区渋谷1-16-14 メトロプラザ1F
TEL: 03- 3499-3225
営業時間:11:00~19:00(木曜休)









